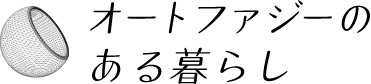日本オートファジーコンソーシアムでは、オートファジーに関する社会的理解の現状や、臨床現場での受け止め方を把握するため、医師の方々を対象としたアンケート調査を実施しました。
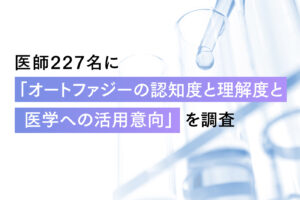
本記事では、その結果をふまえ、コンソーシアムの企業理事でもある松川氏に、医療現場における活用の可能性や今後の展望についてお話を伺いました。
━━まず、今回の医師に対するインタビューを受けての感想をいただけますか?
まず初めに、今回のアンケートにご協力いただいた医師の先生方には、心より感謝申し上げます。
今回のアンケートは、オートファジーコンソーシアムが立ち上がって以来、初めて実施したものであり、このような形での調査は初の試みでした。そうした中で、回答の質も非常に高く、総じて非常に良い結果が得られたと感じています。
医師の認知度・理解度について
━━質問の冒頭ではオートファジーに対する認知度・理解度を確認していますが、この回答については、どうお考えですか?
実はこのオートファジーコンソーシアムでは、オートファジーに関する認知度や理解度について、一般生活者の方々を対象としたアンケートも実施しています。その結果、一般の方の理解度はおおよそ1〜2割程度にとどまっていることがわかりました。
それに対して、今回の医師の皆様へのアンケートでは、約半数、あるいはほとんどの方が、何らかの形でオートファジーについて理解を示しておられました。医師の先生方の理解度の高さが如実に表れた結果であり、大変心強く感じています。また、認知度と理解度の両方において、一般生活者に比べて非常に高く、かつ正確な理解がされていたことも印象的でした。
一方で、「オートファジーはダイエットに良い」といったような、やや誤解を含んだ認識も一部に見受けられました。このような誤解が生まれている点からも、今後このコンソーシアムとして、より正しい情報発信に取り組んでいく必要があることを改めて認識させられました。
社会実装への期待
━━新規治療を含む社会実装の可能性についてはいかがでしょうか?
今回のアンケートでは、社会実装に関する設問、特に新しい治療への応用や、医師の方々が活用していくための支援に関する項目についてもご意見を伺いました。質問3や質問7などがそれに該当しますが、半数以上の先生方から前向きな評価をいただくことができました。
現在の段階では、まだ臨床試験や人への応用といった点では未知数の部分も多い中で、これだけ高い期待を寄せていただけたというのは、非常に心強い結果だったと受け止めています。社会実装に対する期待の高さがうかがえる内容だったと思います。
また、吉森教授がファウンダーである株式会社AutoPhagyGOは現在、健康寿命の延伸を目的とした世界的なコンペティション『XPRIZE Healthspan』にもチャレンジしています。今後、こうした取り組みを通じて新たなデータや成果が生まれてくれば、さらにこの技術や知見に対する期待も高まっていくのではないかと考えています。
━━このような結果が得られた要因と、今後さらに高まっていくためには何が必要と思いますか?
現時点ですでに高い関心が寄せられている背景には、やはり2016年にノーベル生理学・医学賞を受賞した研究であるという点が大きく影響しているのではないかと考えています。
また、医師の先生方ご自身が、高齢化社会における「健康寿命の延伸」という大きな課題に日々直面されている立場でもあるため、オートファジーに対する関心は今後さらに高まっていくのではないかと感じています。
一方で、現段階ではまだ研究途上であるという点もあり、「マーカー」に関する質問では、多くの先生方が「わからない」と回答されていました。関心の高さがある一方で、まだ未知の領域でもあるという現状が、データからも見えてきたと感じています。
今後は、世界に先駆けて「フォーラム標準」を策定していくことが重要になるのではないでしょうか。そして、社会実装という観点から見ても、医療現場で使いやすい指標、つまり今回“副次的なマーカー”と呼んでいるような、直接的なもの以外の活用方法についても、今後どのように取り入れていくかが大きなポイントになってくると考えています。
今後の取組について
━━今後の取り組みとして考えていることはありますか?
そうですね、やはり「フォーラム標準」となるマーカーを策定していくことが、何よりも重要なポイントだと考えています。先ほども触れましたが、長期的にはオートファジーのさまざまな利用シーンを広げていくことも、非常に大切だと思っています。
そのためにも、いわゆる“副次的なマーカー”を同時にしっかりと取得していくことが必要です。こうした副次的なマーカーと主要なマーカーとの相関関係を見ながら、確かな根拠を持って進めていくという視点が大切になると感じています。
私たち企業理事が貢献できる部分としては、やはり社会実装のフェーズをきちんと支えていくことです。現在コンソーシアムでは、企業理事を中心に「認証サプリメント」の形で社会実装を進めており、この取り組みをさらに推進していきたいと考えています。
実際に『XPRIZE Healthspan』の活動の中でも、そうしたサプリメントを提供しながら、食事履歴の管理や栄養の摂取、長期的な運動や睡眠の状況を把握し、あらゆる側面から健康寿命の延伸のための実績づくりに取り組んでいます。
こうした中長期的な視点でのデータ収集や、いわば“コホート研究”に近いかたちでの取り組みが、今後ますます重要になってくるのではないかと考えています。
━━最後に松川様は企業理事と同時に、啓発に関してもかかわられていますが、啓発の重要性についても教えて下さい。
はい、最後にお伝えしたいのは、このコンソーシアムにおける啓発活動の中でも特に重要だと感じていることです。それは、しっかりとしたデータを収集・蓄積し、研究を進めていくこと。そして同時に、正しい情報を社会に向けて発信していき、オートファジーへの理解を深めていただくこと。この「研究」と「情報発信」を両輪として進めていくことが、今後ますます大切になってくると思っています。
そのためにも、単にオートファジーの研究を進めるだけでなく、「人における標準化」、つまり“フォーラム標準”を策定していくことの意義や、そのために必要なマーカーの重要性についても、丁寧に伝えていきたいと考えています。
今回のアンケートとインタビューを通して、医療現場におけるオートファジーの可能性が少しずつ形になりつつあることが見えてきました。今後も現場の声を丁寧に拾いながら、社会実装に向けた取り組みを進めてまいります。

松川泰治
UHA味覚糖株式会社 執行役員 バイオ開発ディビジョン ディビジョンリーダー
京都大学大学院農学研究科修士課程を修了。明治乳業株式会社を経て、UHA味覚糖株式会社に入社。菓子の商品開発に従事した後、ヘルスケア事業を新たに立ち上げた。基礎研究から商品開発までをつなぎ、UHAグミサプリシリーズやオートファジー習慣シリーズなどを研究開発し、商品発売による社会実装を手掛ける。2016年に執行役員に就任し、23年からはバイオ開発ディビジョン、ECディビジョンのリーダーを兼務する。社外でも一般社団法人オートファジーコンソーシアムの理事を務めるなど、新しいヘルスケアの在り方を追求している。